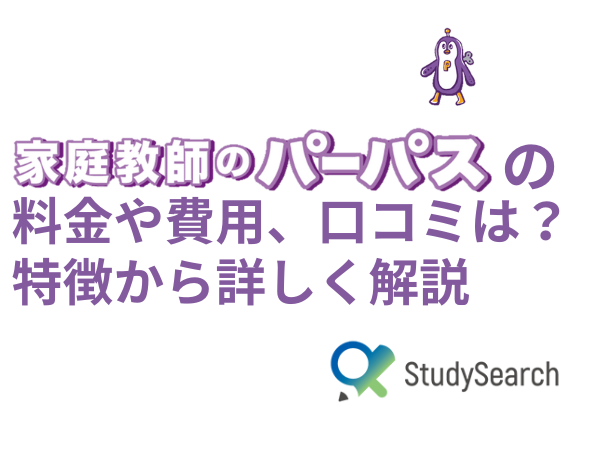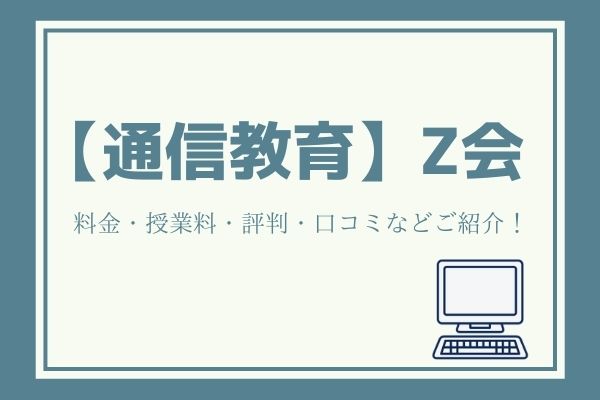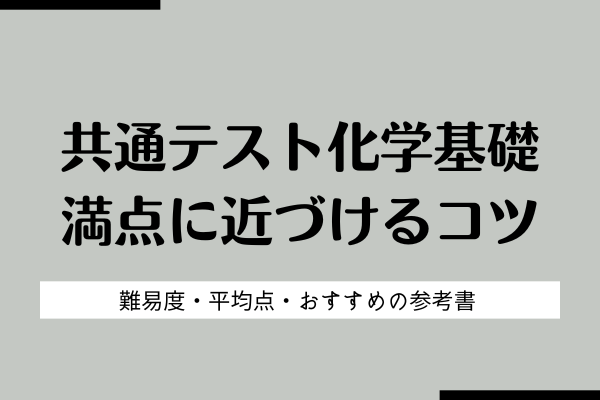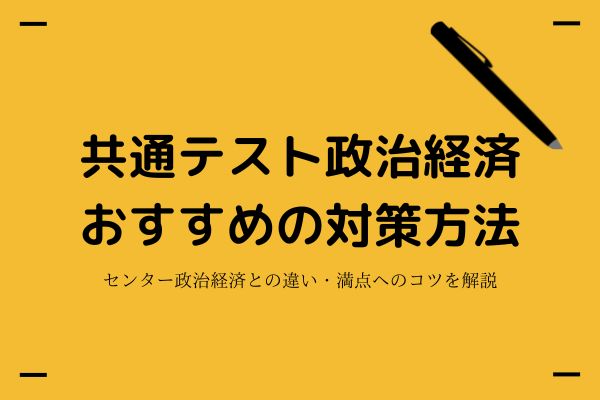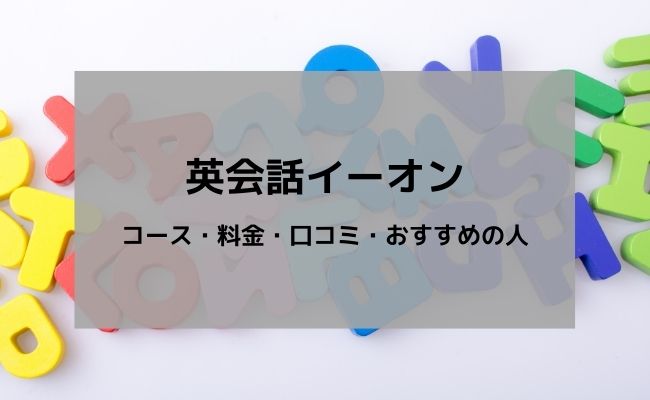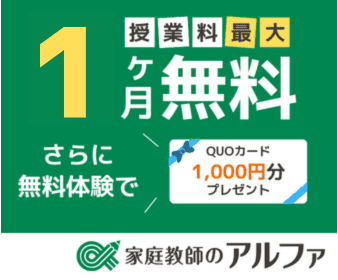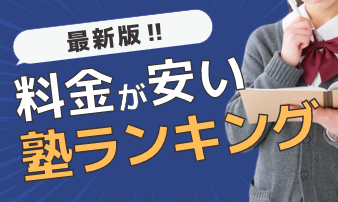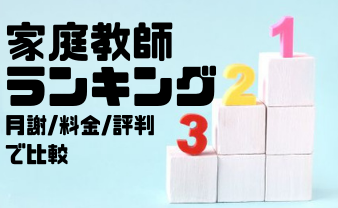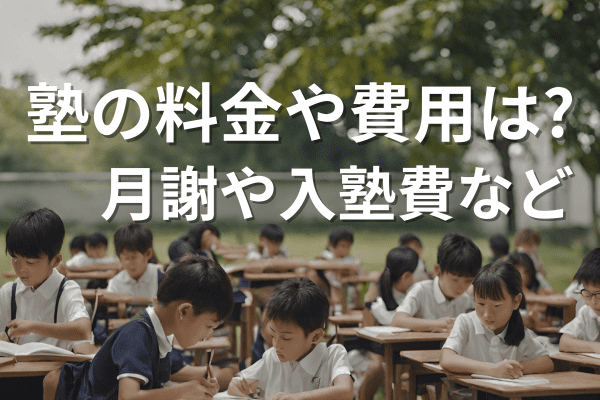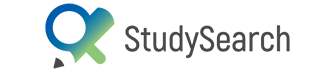【高校教育/大学入試】高大接続改革とは?何が変わるのかを徹底解説
皆さんは「高大接続改革」という言葉をご存知でしょうか。
高大接続改革は2015年1月に発表されました。
教育現場でも徐々に変化が起こっており、特に2021年1月から導入予定の大学入学共通テストはその代表です。
大学入学共通テスト以外にも、高大接続改革の一貫で変わろうとしているものがあります。
今回は、高大接続改革とは具体的に何なのか、高大接続改革で変わること、新入試制度に対応している塾についてお伝えします。
高大接続改革とは
高大接続改革とは、高校教育・大学入試・大学教育が一体になった構造を作る教育改革です。
「学力の3要素」である、1.知識・技能、2.思考力・判断力・表現力、3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を高校・大学教育を通して育成するために、大学入学者選抜で多面的・総合的に評価できるようにします。
グローバル化の進展や人工知能技術などの技術革新、国内生産人口の急減などに伴い、予見の困難な時代で新たな価値を創造していく力を育てることが目的です。
従来の高校教育は、大学入試を通過するため、つまり試験で良い点を取ることが重視されていました。
しかし、高大接続改革によって高校教育を学ぶだけでなく社会で生きる力を伸ばす場に変えることができると考えられています。
✔「高校教育」「大学入試」「大学教育」の三位一体
✔知識や技能、思考力や表現力、主体性が重要
✔高校教育で社会で生きる力を伸ばす
高大接続改革で変わること
高大接続改革で変わることは大きく分けて4つあります。
センター試験から大学入学共通テストへ
2020年度(2021年1月の入試から)、センター試験が廃止され、大学入学共通テストが導入されます。
大学共通テストの導入が発表されたときに含まれていた記述式問題や英語外部試験の導入は中止され、結局何が変わるのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
まだまだ共通テストの情報に関しては不確定な要素も多いですが、すでに以下の変更点が挙げられています。
配点・試験時間の変更があり、特に大きく変化するのは英語です。
英語の筆記とリスニングの配点
センター試験では筆記が200点、リスニングが50点で筆記の配点が8割を占めていました。
大学入学共通テストでは筆記100点、リスニング100点という1:1の配点となります。
リスニング問題音声回数
センター試験ではすべて2回読みで統一されていましたが、大学共通テストでは「1回読み」と「2回読み」で構成されます。
数学1Aの回答時間
センター試験では60分でしたが、10分増加し70分となります。
AO入試・推薦入試の変化
AO入試と推薦入試は、それぞれ「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」という名称に変更されます。
具体的な変更点は2点あります。
出願時期
従来のAO入試は出願が8月1日〜でしたが、総合型選抜では9月1日〜になります。
「早すぎる選考と合格発表は授業の支障になっている」という学校側の意見が反映されました。
学校推薦型入試(推薦入試)の出願時期は変わらず11月1日〜で、合格時期に定めなしから12月1日〜とする規定が定められます。
選考で重視される点
AO入試では大学が求める学生像に基づいて書類と面談で意欲や適性を評価、推薦入試では高校の調査書や小論文、面談等で評価されていました。
このようなAO・推薦入試に対し、「学力が問われない」と批判があったため、小論文や共通テストを導入して学力を問う内容が加えられます。
教科テストなどで「知能や技能」、そして「思考力や表現力」が問うことが必須になりました。
高校の授業内容の変化
授業内容やテストにも変化があります。
高校では2022年度から新たな学習指導要領を導入し、文科省は「学力の3要素」を踏まえて、自ら問題を発見し、自分で考え、他人と協力して解決を目指す力の育成を目指します。
高校では科目の編成が大きく変化します。
国語
現行の国語科目には「国語総合」、「国語表現」、「現代文A」、「現代文B」、「古典A」、「古典B」が含まれ、そのうち「国語総合」のみが共通必修科目となっています。
新学習指導要領で定められた共通必修科目は実生活に生きる「現代の国語」と言語文化への理解を深める「言語文化」です。
さらに選択科目は4科目となります。
現行の「国語表現」に加え、多様な文章を多面的に理解して自分の考えを論理的に表現する能力を育成する「論理国語」、小説や随筆、詩歌の文章の表現を読み味わい、評価するとともに創作能力を育成する「文学国語」、古典を主体的に読み込み、古典の意義や価値について探究する「古典探究」の3科目が新設されます。
英語
現行の「コミュニケーション英語」は、新学習指導要領では「英語コミュニケーション」に変更となります。
また、ディベートやディスカッションを通してスピーキング・リスニング能力、そして発信力を高める「論理・表現」の科目も設置されます。
テストの得点につながるスキルを身につけるだけでなく、中学校までに学んできた4技能5領域の英語を実際にコミュニケーションの手段として用いることを重要視しており、それが科目名にも反映されているのです。
文部科学省は、原則授業は英語のみで行うことや、英語学習のモチベーションともなる「英語を使って何をできるようになりたいか」という学習到達目標を設定することを求めています。
情報
情報科の科目を再編し、「情報I」を新設します。
プログラミング、情報セキュリティなどを含むネットワーク、データの活用のためのデータベースの基礎などを必修化し、情報化社会で活躍できる基礎を固めることが目的です。
大学の3つのポリシー策定・公開義務化
高大接続改革の一角を担う大学入試改革の柱として、2017年より3つのポリシーが定められました。
各大学が策定・公開することが義務付けられています。
ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)
各大学、学部・学科等の教育理念に基づいて、卒業を認定する基準や学位を授与する基準を定めた基本的な方針です。
学生の学修成果の目標とされています。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施方針)
ディプロマ・ポリシーの達成を目指して、どのようなカリキュラムを編成し、どのような教育内容・方法を実施して、学修成果をどのような基準・方法で評価するのかを定める基本的な方針です。
アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)
各大学、学部・学科等の教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づいた教育内容を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基本的な方針です。
受け入れる学生に求める「学力の3要素」を示す役割があります。
なぜ、公開が義務化されたか
3つのポリシーは、入学から卒業までの大学の方針です。
どのような基準で学生を受け入れ、学ばせて、卒業させるのかを公開して、各大学の教育の方向性を明確にしています。
3つのポリシーが公開されることにより、入学希望者が学びたい内容、卒業までに求められる学修成果などについて、入学前から把握することができます。
学びたい内容や将来像と照らし合わせて大学を選択することを可能にするねらいです。
高校教育までで学んだ結果を踏まえて、学生が大学を選びやすくしています。
✔共通テストでは英語のリスニング配点が大幅に増加
✔AO入試、推薦入試には学力試験が追加
✔社会で実用的な科目が追加
新入試制度(総合型選抜)に対応している塾
総合型選抜専門塾AOI
大学入学共通テストでは英語をはじめとして細かい出題傾向の変更などがあり、対応が不安な方も多いのではないでしょうか。
特に総合型選抜(AO入試)を志望している方は、学力が問われるようになると言われても具体的にどのような対策をしていいかわからないと思います。
学習塾は筆記試験に非常に強いカリキュラムを持っているのですが、総合型選抜(AO入試)へのフォローは十分ではないことが多いです。
筆記試験に面接や小論文の対策は必要がないので仕方ないです。
「総合型選抜(AO入試)の対策をしておきたい」という方は、しっかりと対策ができるノウハウを持っている塾を選ぶことが重要です。
総合型選抜(AO入試)に特化したカリキュラムを提供する塾を紹介します。
総合型選抜専門塾AOIとは
総合型選抜専門塾AOIは、生徒一人一人に合わせた合格戦略を作成し、生徒の希望やキャリアビジョンを重要視する総合型入試選抜対策に特化している塾です。
総合型選抜専門塾AOIの特徴
入塾時の成績で志望校を制限せず、本人の「やりたいこと」「将来像」を叶えるため、全力でサポートしてくれます。
総合選抜専門塾AOIでは単なる学力だけでなく、「主体的な学習姿勢」「ロジカルシンキング」「リサーチ力」「自発的に行動する力」「個性と礼節」のスキルを育成します。
またグループワークや宿題などを通じ、自分だけのキャリアプランを構築し、大学別の出願書類を完成させるところまでサポートしてくれます。
入試に必要なテクニックだけでなく、入学後のキャリアデザインまで徹底的にサポートしてくれるのが特徴です。
総合型選抜専門塾AOIの合格実績
総合型選抜専門塾AOIでは、生徒の合格に加え、一人の人間としての成長を目指して指導しているため、全国トップクラスの合格率です。
2019年度入試では、全体合格率92.6%、早慶上智・MARCH合格率85.2%でした。
毎年多くの合格者を輩出しているため、入試データも豊富に蓄積されています。
詳細のわからない新入試制度では、豊富なデータのある専門塾を選ぶべきでしょう。
まとめ
高大接続改革により、「学力の3要素」の育成や多様な学生の受け入れを促進する大学のグローバル化が進んでいきます。
高大接続改革の様々な変更点の中でも、やはり大学入試システムが変わる点が最も学生にとって大きな問題ですよね。
しかし、これらの入試改革によって学生を多面的に見ることができるようになり、さまざまな能力や適性を持つ学生が評価されるチャンスが増えます。
「学力の3要素」をはじめとする多彩な能力を育てることが可能です。
しっかりと変更点やこれから重視される点を確認して学習していって大学入試を突破し、高校・大学でこれからの社会で生きる力を伸ばしていきましょう。
高大接続改革の内容
高大接続改革の内容が一目でわかります。
高大接続改革とは?
高大接続改革とは高校教育・大学入試・大学教育が一体となる改革のことです。
高大接続改革で何が変わるの?
高大接続改革で変わるのは各教科の入試内容や学校教育の内容が変わる可能性があります。
記事内で詳しくまとめているので参考にしてください。
高大接続改革に対応可能な塾は?
高大接続改革に対応可能な塾は総合型選抜専門塾AOIです。
記事内で詳しく解説しているので参考にしてください。
StudySearchでは、塾・予備校・家庭教師探しをテーマに塾の探し方や勉強方法について情報発信をしています。
StudySearch編集部が企画・執筆した他の記事はこちら→
勉強法に関する新着コラム
-
 不登校の生徒におすすめの家庭教師とは?必要な理由や選び方...
不登校の生徒におすすめの家庭教師とは?必要な理由や選び方...不登校の生徒におすすめな家庭教師について紹介していきます。家庭教師の適切な選びかたも解説していますので、不登校の生徒様を持つ保護者の方は必見です!
-
 【2026年最新】安く通える冬期講習9選ご紹介!安く受け...
【2026年最新】安く通える冬期講習9選ご紹介!安く受け...冬期講習を安く抑える方法や冬期講習の相場、冬期講習がある塾を小学生・中学生・高校生で分けておすすめしています。冬期講習を検討中の方は、是非参考にしてみてください...
-
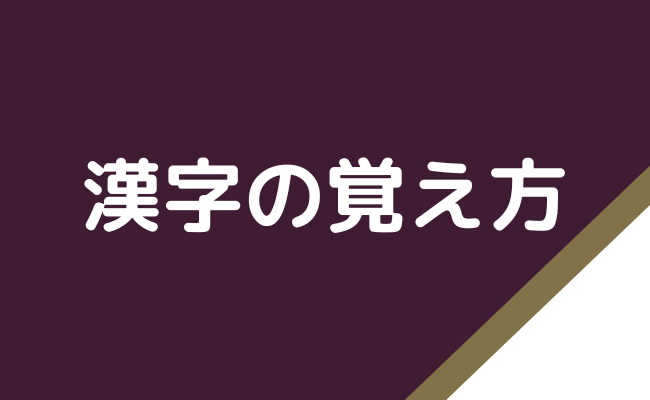 【受験生必見】漢字の覚え方について|覚えるコツや効率良く...
【受験生必見】漢字の覚え方について|覚えるコツや効率良く...本記事では、漢字の覚え方のコツや効率の良い覚え方を伝授します。漢字を習いたての小学生から、漢字の勉強が必要なすべての受験生までどの学年でも通用する方法です。漢字...
-
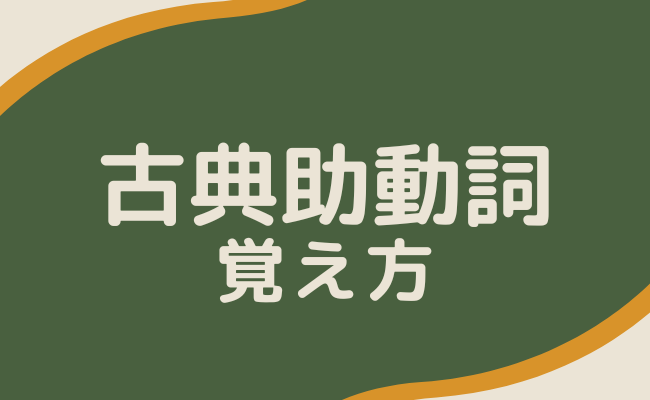 古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...
古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...古典の助動詞がなかなか暗記できない方、効率良く手早く暗記したい方必見!古典の助動詞の覚え方やコツ・覚えやすくなる語呂合わせもご紹介します。古典の助動詞でつまづい...
勉強法に関する人気のコラム
-
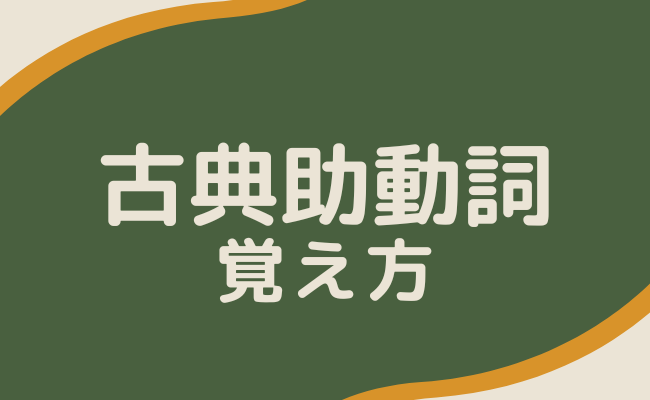 古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...
古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...古典の助動詞がなかなか暗記できない方、効率良く手早く暗記したい方必見!古典の助動詞の覚え方やコツ・覚えやすくなる語呂合わせもご紹介します。古典の助動詞でつまづい...
-
 四則計算のやり方や教え方のポイントを問題とともに分かりや...
四則計算のやり方や教え方のポイントを問題とともに分かりや...四則計算の解き方を分かりやすく解説します。同単元につまずいてしまった方は是非ご覧ください。また、教え方のポイントも紹介しているので、お子様への指導法に悩んでいる...
-
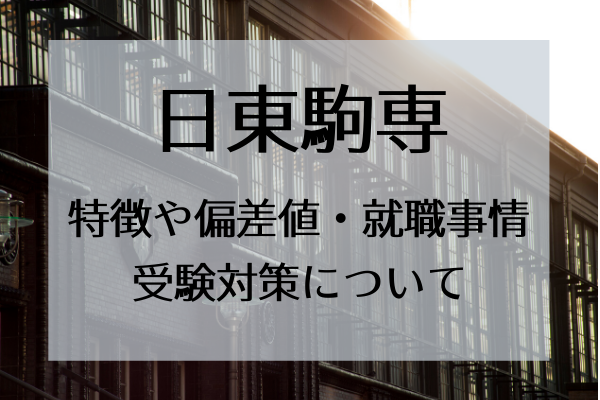 日東駒専が難化傾向に!偏差値や日東駒専に強い塾・予備校に...
日東駒専が難化傾向に!偏差値や日東駒専に強い塾・予備校に...日東駒専の入試が難化した原因・理由はいったい何なのでしょうか? そして日東駒専の最新の偏差値や日東駒専に強い塾、日東駒専に合格するための勉強法も紹介していきま...
-
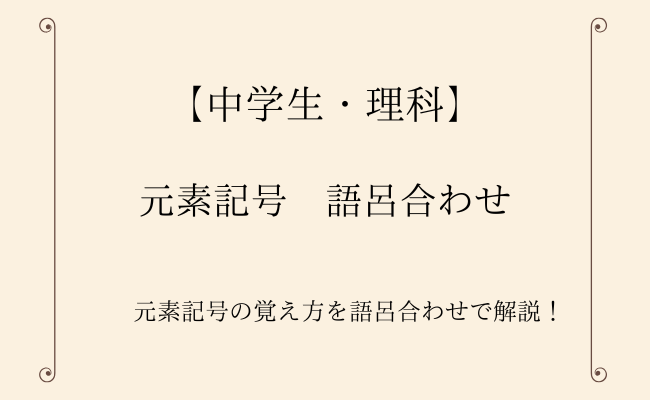 【中学生・理科】元素記号の覚え方とは?語呂合わせの覚え方...
【中学生・理科】元素記号の覚え方とは?語呂合わせの覚え方...こちらの記事では、中学生で習う元素記号の覚え方を語呂合わせで解説しています。各原子番号ごとの覚え方やテストで出る原子記号も詳しく解説していますので、苦手克服や予...