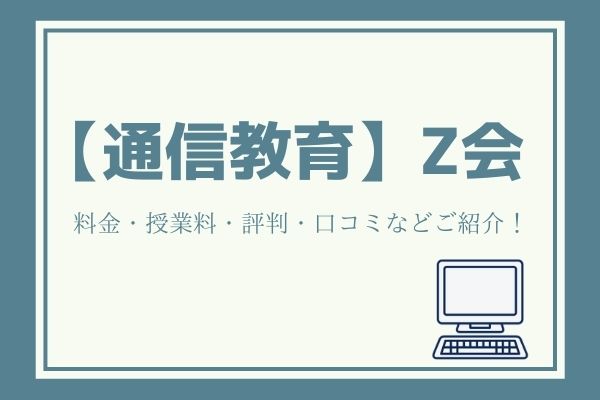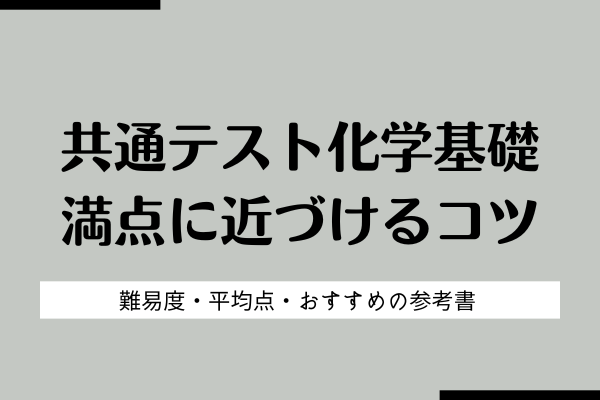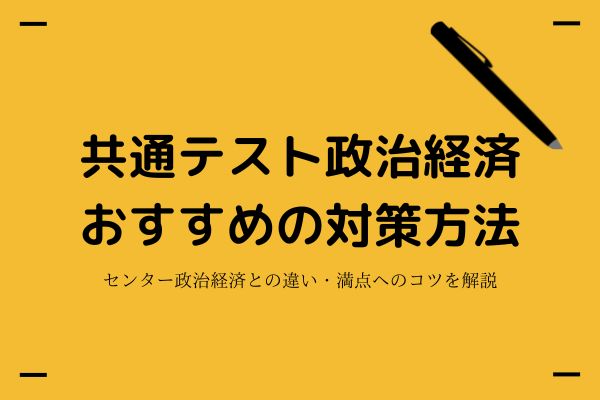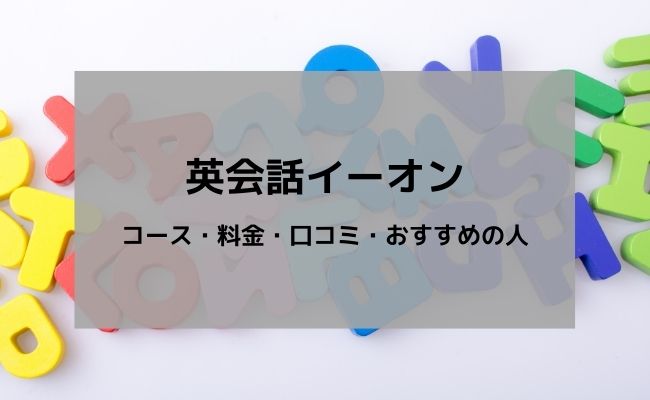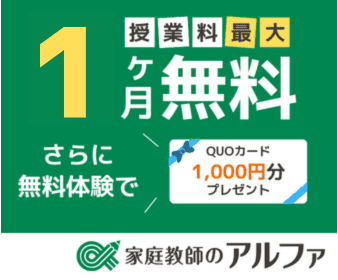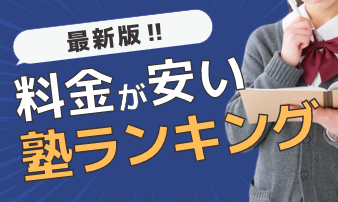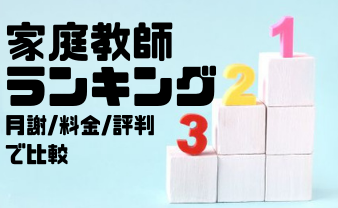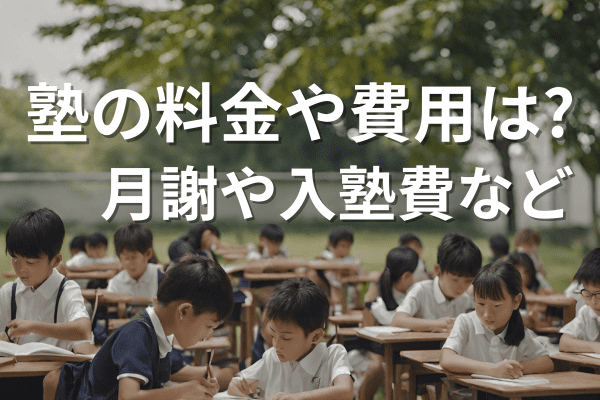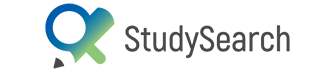おすすめの古文単語帳や勉強法とは?古文の出題傾向も解説
学生のみなさん、古文単語帳はどれがおすすめなのか迷っていませんか?
古文単語帳はそれぞれで特徴が異なり、選ぶのに一苦労している方もいると思います。
ゴロゴや、マドンナ、古文単語帳330など色々あって目移りしてしまいそうです。
当記事では、そのような単語帳の使い方や勉強方法を解説していきます。
ぜひ、気になった方は、当記事を読んでみて下さい。
古文単語帳の選び方
一単語の意味が複数書いてあるもの
大学入学共通テストでは、本来の意味よりも派生の意味が使われることがよくあります。
例えば、「おもしろし」という単語は「趣がある」といった意味ですが、この単語の他の意味である「珍しい」といった意味が使われるということです。
そのため、本来の意味+α1~2個ほど意味が載っている単語帳がおすすめです。
例文が書いてあるもの
大学入学共通テストの古文では単語はもちろん必須です。
大学入学共通テストでは決まって単語問題が15点(3問)出題され、実に3割は単語訳になります。
50点満点中の15点をとるために単語を勉強しなければいけないのはお分かりいただけたでしょうか。
しかし、裏を返せば残りの35点が文章読解、あるいは文法の問題になるということになり、文章で単語がどのように使われているか知っておく必要が出てきます。
そのため、単語を覚えながら例文を見れれば一石二鳥の効果が期待できます。
イラストが掲載されているもの
古文単語を覚える際には、イラストは絶大な効果を発揮します。
古文単語の中には、表記からは想像もつかないような意味を持っている単語が存在します。
例えば、「念ず」という単語は「祈る」といった意味はイメージしやすいかもしれませんが、実は「我慢する」といった意味も持っています。
「こころにくし」という単語は表記からはイメージしづらく、「奥ゆかしい」といった意味を持っています。
このように、意味をイメージしにくい単語でも、イラストがあれば非常に分かりやすくなります。
実際筆者もイラスト付きの単語帳を使い、大学入学共通テストでは古文で満点を取得しました。
そのため、古文単語を勉強する時はイラスト付きの単語帳がおすすめです。
✓一単語の意味が複数書いてあるもの
✓例文が書いてあるもの
✓イラストが掲載されているもの
おすすめの古文単語帳3選
【早稲田生がおすすめ】マドンナ古文単語230
基本的には基礎レベルに対応している単語帳です。
使い方によっては早慶レベルにも対応可能になっています。
語数は230語と少ないように感じるかもしれませんが、関連語なども含めると380語以上になり、非常に内容が濃い単語帳です。
まずは大見出しのところから覚えて、次に、関連語などの細かい部分を覚えていくのがマドンナ単語帳の使い方です。
また、このように勉強をすれば難関大も十分に狙うことができるでしょう。
【イラストがおすすめ】読んで見て覚える重要古文単語315
例文やイラスト、単語のニュアンスの説明など、単語の大見出しに加え様々な要素で構成されています。
これらは暗記をよりスムーズにできるようになるので、ぜひ活用すべきです。
見出し語とその意味だけを機械的に暗記するだけだと、長期的には覚えづらい記憶になりがちで、忘れることが多くなってしまいます。
そのため、上記したようにイラストや例文などにしっかり目を向けて、1つの単語に対し様々なイメージをもたせることで、暗記に役立てましょう。
【初めて使う単語帳におすすめ】Key&Pointみるみる覚える古文単語300+敬語30
右ページにまとめて古文単語、意味、解説、関連語が記載されており、関連する例文や口語訳は左ページに記載されています。
見出し語300語と敬語30語を五つの章に分けて収録、基本から応用・発展へと段階的に学習することができます。
この単語帳は、各語のイメージの幹となるKey、学習上の留意点を簡潔に示したPoint、Check!!問題の順番で単語を暗記していくことで、効率的に古文単語を覚えることができます。
また、本の右ページは、シンプルなのですが簡略に記載されているのではなく、大事なことだけ記載されています。
そのため、初めて古文単語帳を手に取る方におすすめです。
| マドンナ古文単語230 | 読んで見て覚える重要古文単語315 | Key&Pointみるみる覚える古文単語300+敬語30 |
|---|---|---|
| ・丁寧な解説が欲しい ・基礎から勉強したい ・MARCH以上にも使いたい |
・使いやすい例文とイラストが欲しい ・1冊で古文常識や和歌の用法などを知りたい |
・初めての古文単語帳を探している ・シンプルなデザインが好き |
大学入学共通テスト 古文の出題傾向
単語・文法・読解がミックス
今までの大学入学共通テストでは「古文単語のみ」を問題としたものが出題されていましたが、共通テストでは文章読解や内容説明といった教材に対する理解度を測る内容の問題が出題されやすくなっています。
本文となる古典文学以外に資料としてその文章に関する解説文などから内容を読み解く必要もでてきます。
共通テストの古文は単純に古典の単語のみを勉強するのではなく、総合的に文章の読解を中心とした勉強をする必要が強くなりました。
難化した問5
武田塾のリサーチによると問5が非常に難しくなったとのことです。
実際、設問が非常に長くなり、和歌の本歌取りというテクニックについての問題や、教師と生徒の会話形式の問題などあまり触れたことがないタイプの問題のように見受けられます。
本歌取りなどは、初見でその概念を理解するのは困難です。
問1~問4までは大学入学共通テスト対策で対応できますが、問5は専用の参考書での対策が必要になってくるでしょう。
そのため、対策していない人にとってはかなり難しい問題になってきます。
本文の細分化
今まで行われていた大学入学共通テストの古文では、比較的長い文章を読み、内容を問う問題がほとんどでした。
この場合、前半部分で内容が理解できなくなればあとの問題がほとんど不正解になってしまうということが多々ありました。
それに対して、共通テストでは、生徒と先生の会話文を読ませたり、3つの短い文章を読ませたりと、一つの問題文に集中させるのではなく複数の文章に細分化させる傾向が多くなってきました。
そのため、大学入学共通テストに比べて比較的解きやすくなるかもしれません。
しかし、和歌や生徒と先生の対話文をなど短い文章の問題が多数出題される可能性があり、十分な対策は必要になってきます。
✓すべてを満遍なく勉強する必要がある
✓難しくなった問5
✓細かい問題文が多くなる
古文対策におすすめの塾・予備校
上記で述べた、勉強法を塾や予備校ではさらに詳しく知ることができます。
また、塾や予備校は豊富な過去問やテスト問題を持っているため、実践でさらに古文を安定させたいといった方は塾に通うという選択肢も視野にいれるといいでしょう。
個別教室のトライ

| 個別教室のトライの基本情報 | |
|---|---|
| 対象 | 小学生・中学生・高校生・高卒生 |
| 指導形態 | 個別指導 |
| 展開地域 | 全国 |
トライ式学習法
個別教室のトライでは、トライ式学習法で学習効果を最大化させます。
トライ学習法とは、マンツーマン指導の効果をより高めるために編み出されたトライ独自のオリジナル学習法です。
例えば、脳科学理論を応用した「トライ式復習法」では、学習して1時間以内・学んだ日の夜とその翌日に復習する時間を確保することで、覚えた知識を記憶に定着させることができます。
また、トライでは「ダイアログ学習法」を取り入れており、講師が一方的に授業をするのではなく、講師が指導した内容を生徒が説明する時間をつくることで、「わかったつもり」を防ぎます。
このように、古文が苦手な方でも復習を徹底することで学んだ知識を忘れないようにすることができます。
東京個別指導学院

| 東京個別指導学院の基本情報 | |
|---|---|
| 対象生徒 | 小学生・中学生・高校生・高卒生 |
| 対象地域 | 首都圏を中心に全250の直営教室を展開 |
| 指導方法 | 最大1対2までの個別指導 |
| 自習室情報 | あり(教室により要確認) |
| 特徴 | 「成績向上・結果」「講師」で顧客満足度の高い指導 |
きめ細かい講師のサポート
東京個別指導学院では、授業内で演習と解説が効率良くできる1対2の授業か、講師が付きっきりでフォローしてもらえる1対1の授業か 選択することができます。
講師は、授業の中で対話を多く入れ込み、生徒の思考力や表現力を育てています。
正しい答えよりも、正しい答えを導く過程にも目を向けて、定着を図ります。
授業のたびに、講師は生徒の学習状況や進捗状況を把握して、足りない部分や抜けている部分があれば臨機応変に対応してもらえます。
東京・関西個別指導学院の料金・費用
東京・関西個別指導学院の料金・費用は以下の通りです。
| 東京・関西個別指導学院の料金・費用 | |
|---|---|
| 入会金 | 無料 |
| 授業料 | 授業料シミュレーションで確認する⇒ |
| 教材費 | |
東京・関西個別指導学院では、生徒ごとに最適なカリキュラムで指導を行っており、料金が一人ひとり異なります。
入会金や維持費などの追加費用は今後も一切かからないため、保護者様にも安心してご利用いただけます。
授業料シミュレーションにて、あなたに合わせた料金を簡単に知ることが出来ますので、料金の詳細が気になる方は以下の公式サイトよりお気軽にご確認ください。
東京・関西個別指導学院のコース
東京・関西個別指導学院のコースは以下の通りです。
| 学年 | コース |
|---|---|
| 高校生 コースの詳細を確認する⇒ |
大学受験対策 |
| 総合型選抜・推薦対策 | |
| 定期テスト・評定対策 | |
| 中学生 コースの詳細を確認する⇒ |
高校受験対策 |
| 推薦入試対策 | |
| 定期テスト・内申点対策 | |
| 小学生 コースの詳細を確認する⇒ |
中学受験対策 |
| 学習習慣定着サポート | |
| 英語検定対策 |
東京・関西個別指導学院では、上記のコース以外にも様々なコースを用意しています。
お子さまに合わせた専用のカリキュラムを作成いたします。
学習状況や目標に合わせて、コースを選択することができますので、コースの詳細やカリキュラムについて詳しく知りたい方は以下の公式サイトよりお問い合わせください。
東京・関西個別指導学院の校舎見学
東京・関西個別指導学院は、全国に約270教室あります。
| 東京・関西個別指導学院の校舎情報 | |
|---|---|
| 校舎情報 (東京個別指導学院) |
【関東】東京・神奈川・千葉・埼玉 【東海・九州】愛知・福岡 東京個別指導学院の教室情報を確認する⇒ |
| 校舎情報 (関西個別指導学院) |
【関西エリア】京都・大阪・兵庫 関西個別指導学院の教室情報を確認する⇒ |
東京・関西個別指導学院では、校舎見学を実施しています。
校舎見学では、校舎の雰囲気や指導スタイルを実際にご覧いただきながら、学習の進め方や受験対策について個別に相談が可能となっています。
教室の設備や通学の利便性なども確認できるため、安心して塾選びをすることができます。
また、実際の授業の様子やカリキュラムについても詳しくご説明し、納得のいく形で学習をスタートできるようサポートします。
以下の公式サイトより簡単に校舎見学へお申し込みをすることができますので、お気軽にお問い合わせください。
東京・関西個別指導学院のキャンペーン
| 東京・関西個別指導学院の無料キャンペーン | |
|---|---|
| 学習相談 学習相談はこちらから⇒ |
勉強方法や学習の悩みを相談できる |
| 受験相談 受験相談はこちらから⇒ |
受験情報収集に活用したり 受験対策を相談できる |
| 体験授業 体験授業はこちらから⇒ |
希望科目を無料で受講できたり 担当の先生との相性など確認できる |
東京・関西個別指導学院では、無料体験授業等のキャンペーンを実施してます。
全て無料で実施しており誰でも受けられるので、お得な今体験してみましょう。
東京・関西個別指導学院の学習相談
東京・関西個別指導学院では、無料の学習相談を実施しています。
- つまずきの原因がわかる
- 最新の受験情報がわかる
- 勉強法や対策をアドバイスが受けられる
学習相談では、学習の悩みの原因を明確にし、適切な勉強方法を提案します。
また、ベネッセグループの豊富な情報と独自のネットワークを活用し、最新の受験・教育情報を提供します。
無料の学習相談会を通じて、お子さまに最適な指導を見極められますので、是非お気軽にご相談ください。
学習相談は、集団形式ではなく各家庭に個別で実施しているため、安心してご参加ください。
東京・関西個別指導学院の受験相談
東京・関西個別指導学院では、学習相談のほかに受験相談も実施しています。
- 個別に最適化させた受験戦略がわかる
- 豊富な受験情報を知れる
- 相談を通じた最適な学習環境の提案
東京・関西個別の受験相談では、お子さま一人ひとりに最適な受験戦略を提案します。
ベネッセグループの豊富な進学データと独自の情報網を活用し、最新の受験情報を基に志望校別の対策をアドバイスします。
過去の傾向を踏まえた学習プランや効果的な勉強法をご提案し、お子さまに合った受験対策を一緒にプランニングします。
さらに、無料相談を通じて最適な学習環境を見極め、納得のいく形で受験準備を進めることが可能です。
受験に関して不安を感じている方はぜひ一度受験相談を行ってみてください。
東京・関西個別指導学院の体験授業
東京・関西個別指導学院では、体験授業も実施中です。
詳細は以下の通りです。
- 希望科目の授業を無料で体験できる
- プロに学習・進路相談ができる
- 相性や雰囲気を確かめられる
体験授業では、指導経験豊富な教室長によって学習カウンセリングが行われます。
また、授業ではテスト対策や受験対策などをカウンセリング内容に基づいて実際の授業のように行います。
そして、お子様だけでなく保護者の方の相談も受け付けておりますので、学習に関するお悩みを解消することが出来ます。
無料体験授業の流れとしては以下の通りです。
- 無料学習相談
- 学習や授業内容の相談
- 実際に授業を体験
- 学習計画をご提案
体験授業は夕方~夜にかけて行われるため、習い事や部活で忙しい方もご安心ください。
また、校舎見学だけも可能なので、是非お気軽にお申し付けください。
大学受験ディアロ
| 大学受験ディアロの基本情報 | |
|---|---|
| 対象 | 中学生・高校生 |
| 指導形態 | 映像授業 |
| 教室一覧 | 浦和校、海老名校、海浜幕張校、亀戸校、国分寺校、桜新町校、三軒茶屋校、静岡校、新浦安駅前校、新小岩校、水道橋校、巣鴨校、センター南校、船橋校、三鷹校、茗荷谷校、武蔵浦和校、早稲田校 |
こだわりの学習スタイル
正解が何かではなく「なぜそう考えたか」をトレーナーの方は常に問いかけています。
自ら言葉にしていくことで考えが整理され「そういうことか!」という気づきが起きます。
この気づきは印象度合いが高く、理解が深まります。
これは科学的に証明されており、オートクライン効果と呼びます。
ディアロでは意図的にこの効果を高めて、指導を行っています。
この指導の効果により、慶應義塾大学や早稲田大学などの名門大学にも多数合格しています。
講師からの充実したサポートが受けられる東京個別指導学院
✓「なぜ」を深堀りしていく大学受験ディアロ
古文の勉強法
古文単語の勉強法
1冊を徹底的に使おう
実は、古文単語集は英語と同様何冊も購入し、学習する必要はないです。
標準レベルの単語集1冊、例えば上記で紹介したマドンナ古文230などを繰り返し、一冊を仕上げることに重点を置いて単語帳を使います。
やみくもに多くの単語を丸暗記するのではなく、実際の文章の中で単語のどの用例にあてはまるのかを理解し使える知識にしておくことが重要になってきます。
テストで単語帳以外の単語が出てきたとしても、一冊を完璧に仕上げておくだけで前後の単語から類推することは可能です。
そのため、まずは一冊を完璧に仕上げることを目標にしましょう。
現代語との関わり・違いを意識
古文単語を覚える際には、現代語との関わりや違いを意識して暗記すると効率的です。
その際には、現代語とは違う意味を持つもの、現代に残る言葉の語源となったものなどに注意をしましょう。
そして、その現代語訳よりも単語の持つ感覚・イメージを先に覚えた方が暗記がしやすくなります。
最初は、ニュアンスで単語を捉えてしまって大丈夫です。
最初からいきなり覚えようとするとなかなか覚えにくく、イメージを持っていればあとから意味が自然と付いてきます。
そのため、イメージ→具体化の順が非常におすすめの方法です。
古文文法の勉強法
活用・接続を先に覚えよう
「活用」は古文を読む上で欠かせない知識でありながら、覚えるべきことは意外と少なくて済みます。
「活用」を覚える順番としては、一番使う「動詞・形容詞・形容動詞の活用」、次に「助動詞の活用および接続」、最後に、「助詞の接続」の順番で覚えるようにしましょう。
動詞などの活用形はよく使われるため、問題を解く上では早めに覚えて置きたいところです。
そして、「助詞」や「助動詞」は現代語と似ている部分があるため、比較的楽に覚えられると思います。
敬語を覚えよう
古文の読解においてかなり重要になってくるのが敬語です。
敬語の種類には「丁寧語」「尊敬語」「謙譲語」の3種類があり、その分類によって誰から誰に敬意が向いているのかが異なってきます。
主語や目的語が省略されやすい古文では、この敬意の方向が主語を見極めるヒントになることがあり、敬意の方向が分からなければ解けないような問題も出題されます。
それゆえ、それぞれの敬語が「誰から誰への敬意を表現するか」をおさえることは、古文をマスターする上で必須条件となってきます。
勉強したのに点数が取れない、古文の実力が伸びない、安定しないという方はこの部分をないがしろにして多くの読解を行っている場合が非常に多いので注意するようにしましょう。
✔古文単語は現代語との関わり違いを意識して覚える
✔文法は活用・接続・敬語が大切
まとめ
これまで、古文の単語帳や勉強方法について解説を行ってきました。
古文は現代文に比べて、暗記をするだけで得点を上げることが可能な教科です。
まずは、単語を覚え、文法を学びそこから問題をとき始めるとより問題が理解しやすくなるのではないでしょうか。
また、苦手意識が芽生えることも減らせるはずです。
当記事が、学生の皆様の助けになると幸いです。
-->【初心者でもわかる】この記事のまとめ
「古文単語帳」に関してよくある質問を集めました。
古文単語帳の選び方は?
大学入学共通テストでは、本来の意味よりも派生の意味が使われることがよくあります。そのため一単語の意味が複数書いてあるもの、またイメージがしやすいように例文が書いてあるもの、イラストが掲載されているものがおすすめです。詳しくはこちらを参考にしてください。
おすすめの古文単語帳は?
おすすめの古文単語帳は「マドンナ古文単語230」、「読んで見て覚える重要古文単語315」、「Key&Pointみるみる覚える古文単語300+敬語30」の3つです。目的やレベルよっておすすめしたい参考書は異なります。記事で詳しくまとめましたので こちらをご覧ください。
古文単語の勉強法は?
まずは単語帳を繰り返し解き、一冊を仕上げることに重点を置いて単語帳を使います。やみくもに多くの単語を丸暗記するのではなく、実際の文章の中で単語のどの用例にあてはまるのかを理解し使える知識にしておくことが重要になってきます。また古文単語を覚える際には、現代語との関わりや違いを意識して暗記すると効率的です。詳しい内容はこちらをご覧ください。
StudySearchでは、塾・予備校・家庭教師探しをテーマに塾の探し方や勉強方法について情報発信をしています。
StudySearch編集部が企画・執筆した他の記事はこちら→
勉強法に関する新着コラム
-
 不登校の生徒におすすめの家庭教師とは?必要な理由や選び方...
不登校の生徒におすすめの家庭教師とは?必要な理由や選び方...不登校の生徒におすすめな家庭教師について紹介していきます。家庭教師の適切な選びかたも解説していますので、不登校の生徒様を持つ保護者の方は必見です!
-
 【2026年最新】安く通える冬期講習9選ご紹介!安く受け...
【2026年最新】安く通える冬期講習9選ご紹介!安く受け...冬期講習を安く抑える方法や冬期講習の相場、冬期講習がある塾を小学生・中学生・高校生で分けておすすめしています。冬期講習を検討中の方は、是非参考にしてみてください...
-
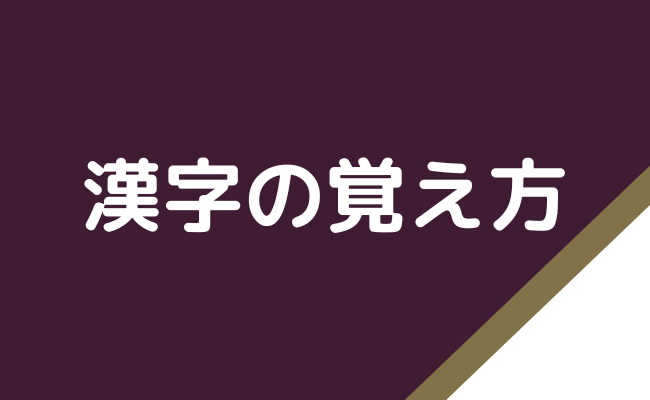 【受験生必見】漢字の覚え方について|覚えるコツや効率良く...
【受験生必見】漢字の覚え方について|覚えるコツや効率良く...本記事では、漢字の覚え方のコツや効率の良い覚え方を伝授します。漢字を習いたての小学生から、漢字の勉強が必要なすべての受験生までどの学年でも通用する方法です。漢字...
-
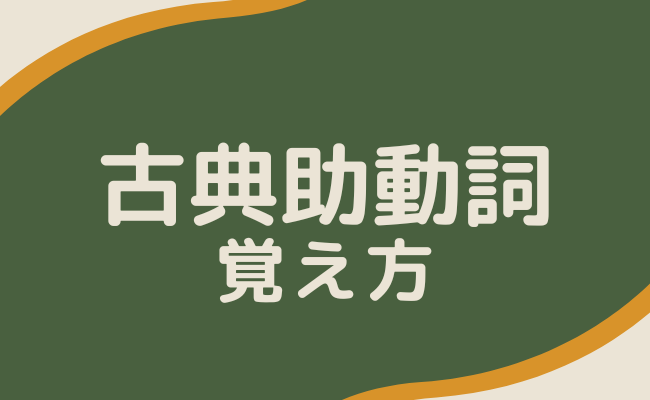 古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...
古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...古典の助動詞がなかなか暗記できない方、効率良く手早く暗記したい方必見!古典の助動詞の覚え方やコツ・覚えやすくなる語呂合わせもご紹介します。古典の助動詞でつまづい...
勉強法に関する人気のコラム
-
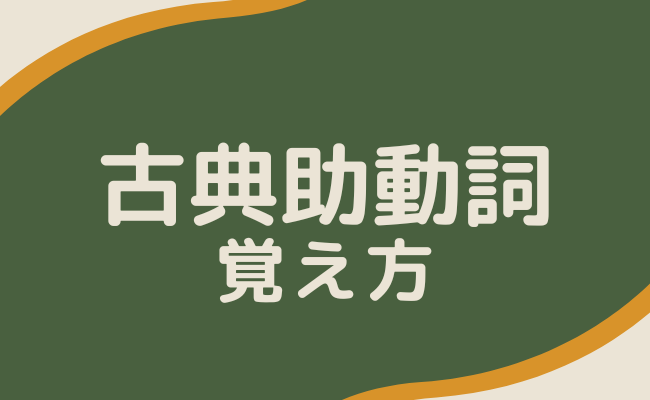 古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...
古典の助動詞を効率良く覚えよう!語呂合わせや覚え方・コツ...古典の助動詞がなかなか暗記できない方、効率良く手早く暗記したい方必見!古典の助動詞の覚え方やコツ・覚えやすくなる語呂合わせもご紹介します。古典の助動詞でつまづい...
-
 四則計算のやり方や教え方のポイントを問題とともに分かりや...
四則計算のやり方や教え方のポイントを問題とともに分かりや...四則計算の解き方を分かりやすく解説します。同単元につまずいてしまった方は是非ご覧ください。また、教え方のポイントも紹介しているので、お子様への指導法に悩んでいる...
-
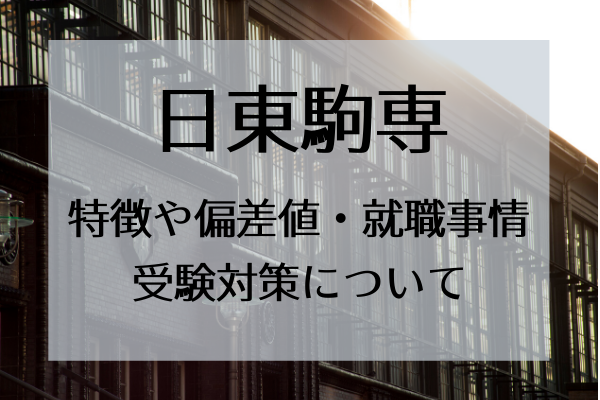 日東駒専が難化傾向に!偏差値や日東駒専に強い塾・予備校に...
日東駒専が難化傾向に!偏差値や日東駒専に強い塾・予備校に...日東駒専の入試が難化した原因・理由はいったい何なのでしょうか? そして日東駒専の最新の偏差値や日東駒専に強い塾、日東駒専に合格するための勉強法も紹介していきま...
-
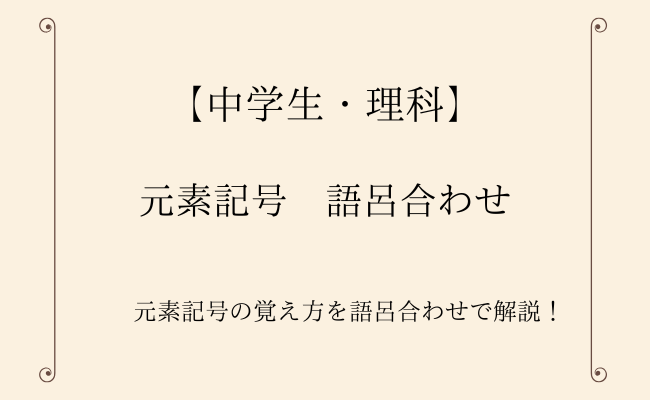 【中学生・理科】元素記号の覚え方とは?語呂合わせの覚え方...
【中学生・理科】元素記号の覚え方とは?語呂合わせの覚え方...こちらの記事では、中学生で習う元素記号の覚え方を語呂合わせで解説しています。各原子番号ごとの覚え方やテストで出る原子記号も詳しく解説していますので、苦手克服や予...