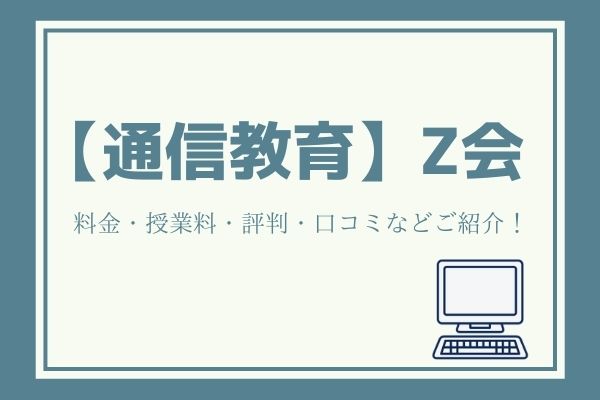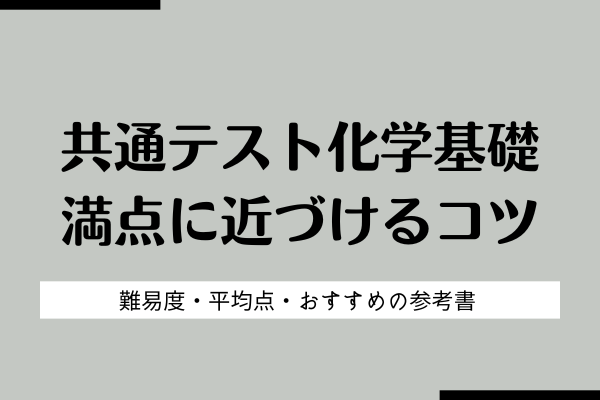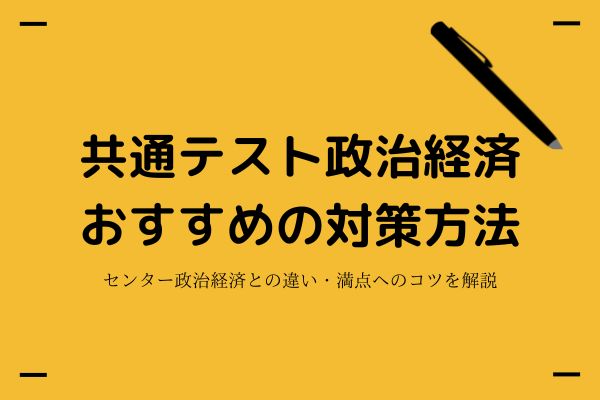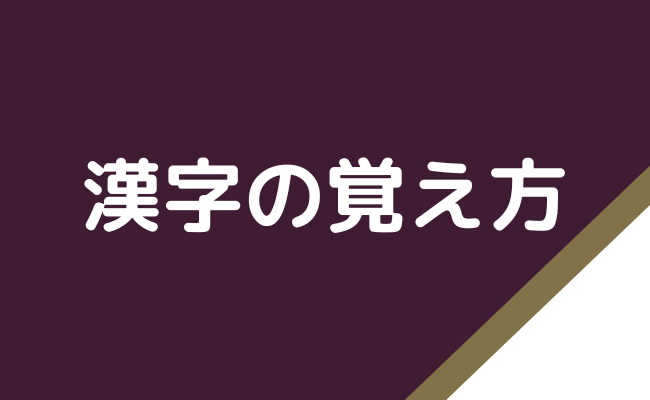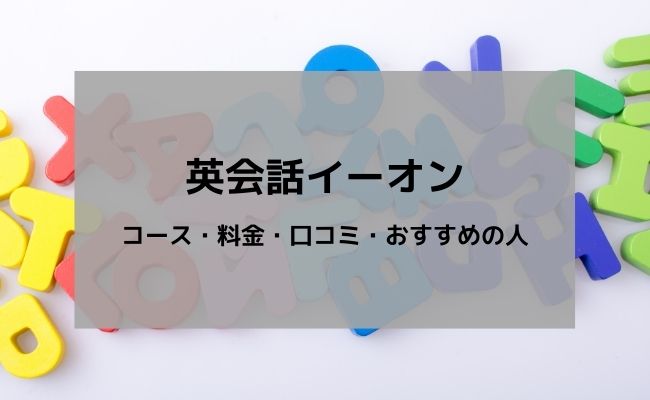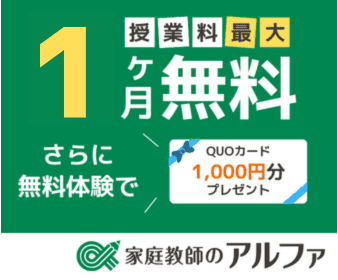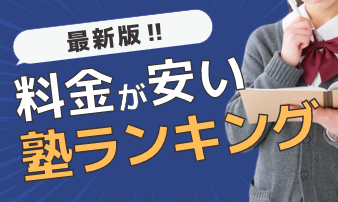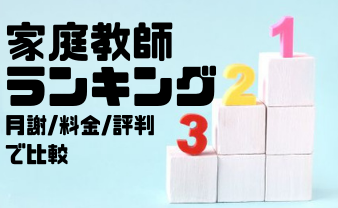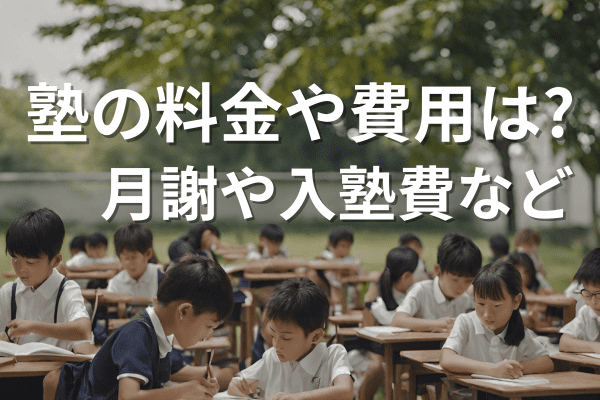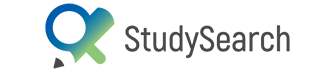数学検定3級の難易度は?合格率や対策・勉強法/おすすめの参考書をご紹介
この記事では、数学検定3級の難易度や対策、おすすめの参考書などについて解説していきます。
「数検3級のレベルってどのくらい?範囲はどうなの?」
「数検3級の合格率って高いの?」
こうした疑問や悩みを抱えている方は、ぜひ読んでみて下さい。
また、数検対策におすすめの塾についても紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。
■まとめ
数学検定3級とは?
数学検定とは
文部科学省が後援している検定
数学検定とは、正式名称を実用数学技能検定といいます。
計算・作図・統計・証明などを含む数学の実用的な技能を測定、論理構成力をみる記述式の検定として文部科学省が後援している検定です。
また、年に1度、成績優秀な団体及び個人を表彰し、「文部科学大臣賞」を授与しています。
数検の階級
| 数検の階級 | |
|---|---|
| 階級 | 特徴 |
| 5級 | 中学校1年程度の試験 計算問題が30問・数理問題が20問出題される 試験時間は計算問題50分・数理問題60分 |
| 4級 | 中学校2年程度の試験 計算問題が30問・数理問題が20問出題される 試験時間は計算問題50分・数理問題60分 |
| 3級 | 中学校3年程度の試験 計算問題が30問 数理問題が20問出題される 試験時間は計算問題50分数理問題60分 |
| 準2級 | 高校1年(数学Ⅰ・A)程度の試験 計算問題が15問 数理問題が10問出題される 試験時間は計算問題50分・数理問題90分 |
| 2級 | 高校2年(数学Ⅱ・B)程度の試験 計算問題が15問出題され、数理問題は必須問題2題と5題のうちから3題選択する 試験時間は計算問題50分・数理問題90分 |
| 準1級 | 高校3年(数学Ⅲ)程度の試験 計算問題が7問出題され、数理問題は必須問題2題と5題のうちから2題選択する 試験時間は計算問題60分・数理問題120分 |
| 1級 | 大学程度・一般の試験 計算問題が7問出題され、数理問題は必須問題2題と5題のうちから2題選択する 試験時間は計算問題60分・数理問題120分 |
数学検定の各階級の特徴については上記の表のようになっています。
5級から始まり、1級に向かうにつれて徐々に目安となる学年や問題の難易度が高くなっていきます。
数学検定3級は、
問題は、計算問題と数理問題で構成されており、試験時間も各階級で異なります。
数学検定のメリット
- 入試や受験・就活で役に立つ
- 自分の目的に合った級を受験できる
- 自分の力を証明できる
入試や受験・就活で役に立つ
数学検定は、大学・高校・中学によっては
入試優遇が受けられる高校・中学は720校以上、大学・短大・専門学校は440校以上あるようです。
また、大学・高校・高等専門学校などで特定の科目の単位取得が認められる場合もあります。
さらに、就職活動でのSPI試験の対策としても有益です。
自分の目的に合った級を受験できる
数学検定は、5級から1級まで幅広い階級が用意されており、問題の難易度も徐々に上がっていくように設定されています。
これにより、受験者それぞれの学習段階に応じた階級を選んで受験することができ、数学の力を着実につけていくことができます。
自分の力を証明できる
数学検定に合格すると、合格証を発行してもらうことができます。
これにより、数学力が客観的に評価され見える形で表されるので、自分の持つ数学力を証明することができます。
また、就職活動におけるエントリーシートや履歴書への記載も可能で、このことも自分の数学力の証明につながります。
✔入試や就職で使える資格
✔7段階の級に分かれている
✔3級は中学3年生レベル
数学検定3級の試験概要
【2023年】数検の日程
| 2023年 数学検定の日程 | |||
|---|---|---|---|
| 検定日 | 申込期間 | WEB合否確認日 | |
| 第406回 | 4月16日(日) | 2月13日(月)~3月14日(火) | 5月10日(水) |
| 第410回 | 7月23日(日) | 5月22日(月)~6月13日(火) | 8月17日(木) |
| 第414回 | 10月29日(日) | 8月28日(月)~9月19日(火) | 11月16日(木) |
2023年の数学検定の日程は上記の表のようになっています。
2023年は
そして、各回検定日から3週間前後にWEB上で検定の合否の確認をすることができます。
【数検3級】問題の構成
総合50問ある2つの試験を受験
数検3級では、計算技能を測る1次試験と、数理技能を測る2次試験を受験します。
出題数は合計50問で、1次試験で30問、2次試験で20問を解きます。
| 問題構成 | 1次:計算技能検定 2次:数理技能検定 |
|---|---|
| 出題数 | 1次:30問 2次:20問 |
また、問題全体の構成としては、中学1・2・3年生レベルの問題がそれぞれ3割ずつ出題され残りの1割で特有問題が出題されます。
試験で合格基準が異なる
1次、2次とありますが、数検では1度に2つの試験を受けそれぞれの合格基準点を満たした場合に合格となります。
なお、合格基準は1次試験が70%程度の正解率で、2次試験が60%程度の正解率になります。
【数検3級】問題内容と合格率
中学校で習う内容
数検3級の問題の範囲は、中学校で習う内容で構成されています。
| 検定の内容 | 平方根/式の展開/因数分解/円の性質/体積比/平面図形の構成など(一部例) |
|---|
| 技能内容 | |
|---|---|
| ① | 簡単な構造物の設計や計算ができる |
| ② | 斜めの長さを計算することができ、材料の無駄を出すことなく切断したり 行動することができる。 |
| ③ | 製品や社会現象を簡単な統計図で表示することができる。 |
1次試験では、因数分解や二次方程式、角度の計算などが出題されます。
一方2次試験では、速度算や球の表面積や対面積を求める問題、コンパスを使った作図問題などが出題されます。
数学検定3級の合格率
| 実施年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 78,202人 | 84,913人 | 100,924人 |
| 合格者数 | 52,080人 | 52,573人 | 60,480人 |
| 合格率 | 66.6% | 61.9% | 59.9% |
数学検定3級の最近3年間における受験状況は上記の表のようになっています。
受験者数については年々減少傾向にあることが読み取れますが、合格率をみると、どの年も60%前後で安定しているといえそうです。
合格率60%というと、簡単に合格するとはいえないレベルなので、多少なりとも試験対策をして検定に臨むことが必要です。
【数検3級】検定時間や検定料金について
| 検定時間 | 1次:50分 2次:60分 |
|---|---|
| 検定料金 | 個人受検:4,500円 提携会場受験・団体受験:3,500円 |
また、検定料金は個人受験の場合だと4,500円、提携会場受験・団体受験の場合は3,500円になります。
数研の受験料は級が上がるごとに上がっていきます。
✔試験は4月・7月・10月の年3回
✔二次試験まである
✔検定料は個人だと4,500円
数学検定3級の対策・勉強法
数学検定3級の対策・勉強法は、主に3つあります。
参考書や問題集で数学検定に慣れる
数学検定に合格するためには、各級の出題範囲となる
そのために、まずは参考書を使って出題傾向の高い内容を中心に学習を進めてみましょう。
また、問題集で演習に取り組み、参考書で学んだ知識を実際に使ってみることも忘れずに行う必要があります。
問題演習を行うことで、参考書で学んだ内容を本当に理解しているかどうか簡単に確認することができます。
本番同様に試験問題を解く
参考書や問題集を用いた学習が一通り終わったら、過去問に取り組んでみてください。
過去問は数学検定で過去に実際に出題された問題なので、本番同様に時間を計って解くことで
しっかりと自分の実力をつけられるよう、だらだらと時間をかけたり、途中で他のことをしたりすることは禁物です。
過去問演習をたくさん行うことで、本番当日でも落ち着いて試験を受けられるようになるでしょう。
丸付けや復習を必ず行う
問題演習や過去問演習をしたら、すぐに丸付けと復習を行うようにしましょう。
どのように考えて問題を解いたのか鮮明に覚えているうちに丸付けをすることで、間違った問題についてどうして間違えてしまったのか確認しやすくなります。
そして、間違えた理由が分かると次回から意識するようになるので、自然とミスを減らすことにつながります。
また、演習をしていて苦手だと感じた問題や間違えた問題については徹底的に復習することが大切です。
✔出題範囲をまんべんなく学習する
✔過去問で本番に備える
✔苦手分野の克服や復習を忘れずに
数検3級対策できるおすすめの参考書
数学検定3級におすすめの参考書は、以下の2つです。
| 参考書名 | 受かる!数学検定3級 | 数学検定 実用数学技能検定 要点整理3級 |
|---|---|---|
| 出版社 | 学研プラス | 日本数学検定協会 |
| 価格(税込) | 1,100円 | 1,320円 |
受かる!数学検定3級(ステップ式の対策で、合格力がつく!)
1つ目は、学研出版の受かる!数学検定3級(ステップ式の対策で、合格力がつく!)です。
過去問を徹底研究した参考書
この参考書は、過去問を徹底研究したステップ式の構成をとっているため、基礎から確実に数検3級を対策することができます。
また、問題には正答率の表示と細かい解説がついているため、実力の確認と向上もしっかりと行えます。
「数学検定 実用数学技能検定 要点整理3級」
2つ目は日本数学検定協会が編集した数学検定 実用数学技能検定 要点整理3級です。
単元ごとに整理された問題集
この問題集では、問題が単元ごとに整理されて収録されています。
単元ごとに基本事項の確認と難易度別の問題が掲載されているため、基礎から応用レベルにまで着実に学力を向上させることができます。
また、単元ごとに分かれているため、苦手分野のみを集中して学習することも可能です。
過去問題集もおすすめ
『実用数学技能検定 過去問題集 3級』は、日本数学検定協会が出版している過去問題集です。
実際に出題された試験問題とほぼ同じレイアウトで作成されているので、本番と同じような状態で問題に取り組むことができます。
また、解答用紙も本番同様のものが付いているので、より本番を意識した演習をすることが可能です。
解説についても、途中式や問題のポイントが詳しく掲載されているので、確実に自分の実力をアップさせることができるでしょう。
数検対策できるおすすめの塾は?
先程も解説したように、数検対策では専門の塾の利用がおすすめです。
そこで、ここでは数検対策ができるおすすめの塾を紹介したいと思います。
オンライン数学克服塾MeTa

| オンライン数学克服塾MeTaの基本情報 | |
|---|---|
| 対象 | 中学生・高校生 |
| 授業形式 | オンライン(個別1対1、集団) |
| 特徴 | 数学克服・対策に特化したオンライン専門塾 |
オンライン数学克服塾MeTaは、数学に特化したオンライン専門塾です。
生徒一人ひとりに合った数学克服プランを通じて、生徒の苦手克服に尽力しています。
生徒専用カリキュラム
MeTaの特徴は、生徒一人ひとりに合った数学克服プランを通じた、丁寧な指導です。
生徒と講師で面談を行い、生徒の数学克服に適したプランを作成していきます。
個別指導や演習授業の際に進捗具合について相談ができるので、確実にプランを遂行することができます。
オンライン数学克服塾MeTaの実績
MeTaは、岩手医科大学に合格した生徒や、学校の定期テストでクラス内1位を取れるまでに成長した生徒を輩出しています。
このように生徒一人ひとりに合った指導を行ってくれるため、数検対策にもおすすめです。
まとめ
数学検定3級は、中学3年レベルの問題が出題される試験です。
そして、合格率は60%前後のため、難易度は高めだと考えられます。
したがって、合格するためにはしっかりとした対策と勉強が必要です。
数学検定3級の受験を考えている方は、ぜひこの記事で紹介した勉強法や参考書を利用してみて下さい。
また、塾の併用を考えられている方はMeTaの利用もぜひ検討してみて下さい。
【初心者でもわかる】この記事のまとめ
「数学検定3級」に関してよくある質問を集めました。
数学検定3級の合格率・難易度は?
数学検定3級の合格率は、2020年が66.6%、2019年が61.9%、2018年が59.9%となってます。受験者数は毎年減少しており、その分合格率が高くなっています。これ以外の年を見てみても、数学検定3級の合格率は約60%のようです。難易度としては高校入試レベルです。
数学検定3級の対策方法は?
数学検定3級の勉強法としては、まず試験範囲である中学3年生までの学習をまんべんなく復習しておく必要があります。次にある程度の知識が身についたら本番に備えるため、過去問を行いましょう。そして問題を解き間違えたところや復習をしっかり行いましょう。
StudySearchでは、塾・予備校・家庭教師探しをテーマに塾の探し方や勉強方法について情報発信をしています。
StudySearch編集部が企画・執筆した他の記事はこちら→
受験・資格に関する新着コラム
-
 東洋大学牛久高校の偏差値・入試方式・部活動は?制服や進学...
東洋大学牛久高校の偏差値・入試方式・部活動は?制服や進学...東洋大学牛久高校は茨城県牛久市にある中高一貫校です。5つのコースに分かれ偏差値は44-57となっており、一般入試はB入試・C入試・特色型2教科受験が可能です。
-
 italkiとは?料金形態や口コミ、選ばれる理由を徹底解...
italkiとは?料金形態や口コミ、選ばれる理由を徹底解...本記事では、italkiに関する料金形態や口コミ・評判、選ばれる理由や特徴を徹底解説しています。オンラインで英語学習を行いたい方などに最適な英語学習プラットフォ...
-
 多様なニーズに対応した学習塾Enducateの費用や口コ...
多様なニーズに対応した学習塾Enducateの費用や口コ...個別指導の新しい形とは?プロ講師のみの質の高い授業が受けられる、ニーズに合わせた新しい形の学習塾 Enducateの特徴や実績・気になる費用もご紹介!
-
 春期講習を無料で受けられる塾12選!費用の抑え方や料金相...
春期講習を無料で受けられる塾12選!費用の抑え方や料金相...春期講習が無料で受けられる塾を紹介しています。 春季講習の料金相場や費用の抑え方tについても解説しています。
受験・資格に関する人気のコラム
-
 大学無償化とは?条件や支援内容・手続き方法・メリット・注...
大学無償化とは?条件や支援内容・手続き方法・メリット・注...令和2年4月1日から実施の大学無償化についてご存知でしょうか。本記事では家庭での資産/年収での要件や手続き方法・支援によるメリット等を解説します。詳しい内容につ...
-
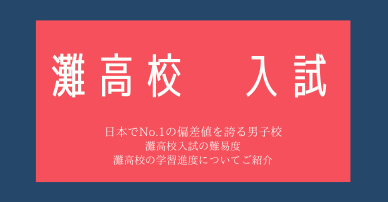 偏差値79|灘中学校・高等学校を解説!偏差値・難易度・入...
偏差値79|灘中学校・高等学校を解説!偏差値・難易度・入...今回の記事は7割が東大入学実績を誇る灘高校についてまとめました。男子校・中高一貫校である灘高校受験の難易度や高校の学習進度について徹底解説いたいします。
-
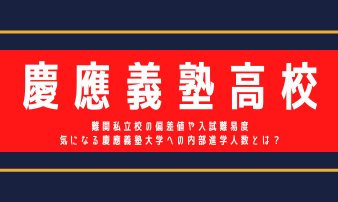 【2026年度】慶應義塾高校を徹底解説!偏差値や入試の難...
【2026年度】慶應義塾高校を徹底解説!偏差値や入試の難...今回の記事は、慶應義塾が経営・運営する中高一貫の男子校である慶應義塾高校の偏差値や入試の難易度についてご紹介します。高校から慶應義塾大学に内部進学する人数や授業...
-
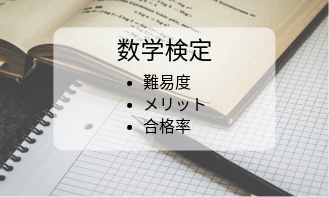 数学検定の難易度や勉強法、メリットとは、合格率や各級のレ...
数学検定の難易度や勉強法、メリットとは、合格率や各級のレ...数学検定の難易度や合格率とは?受けても意味がない?受けることで得られるメリットとは?今回は、そんな印象を持たれる数学検定について詳しく説明していきます。数学検定...