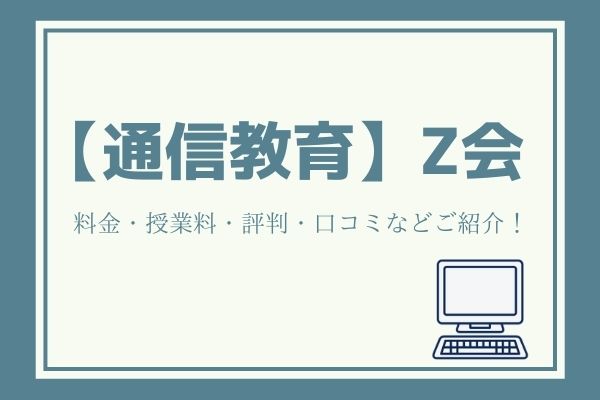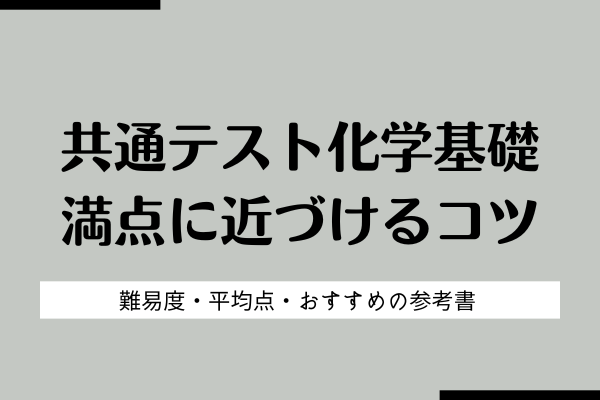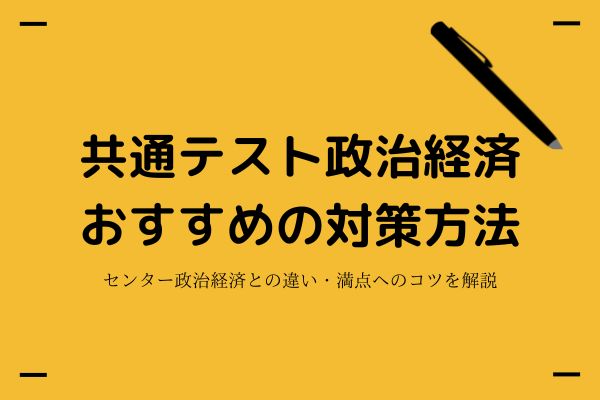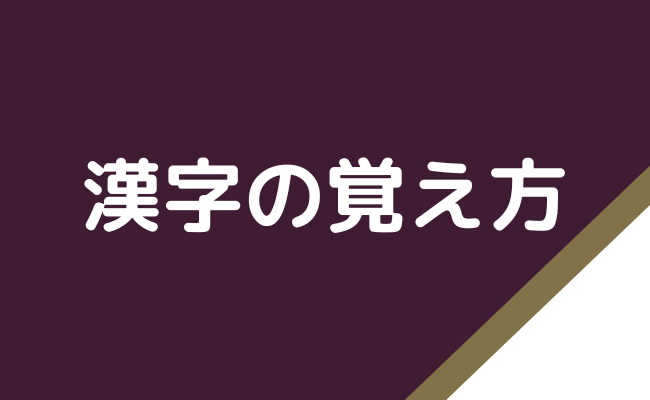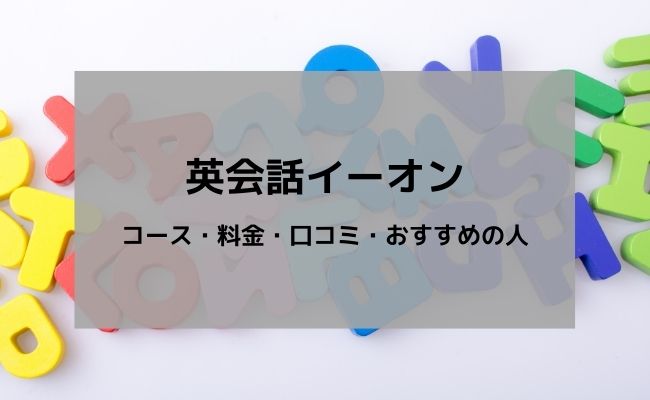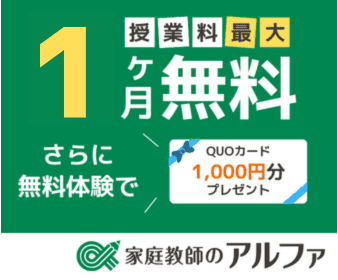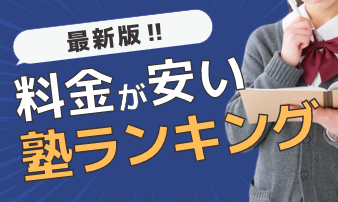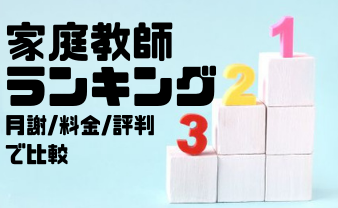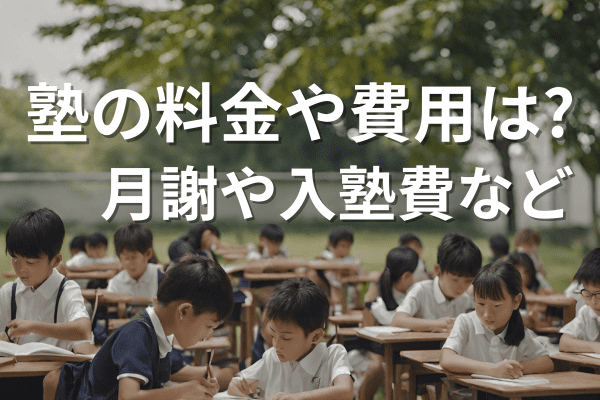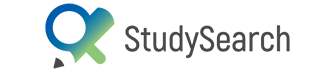学校推薦型選抜(指定校推薦/公募推薦)で変わること|対策について
学校推薦型選抜(推薦入試)は一般選抜と合わせて大学入試の二つの柱とされています。
過去10年ほどの間、学校推薦型選抜の入学者比率は増加していました。
国公立大学では全体の9割以上の大学が実施しており、近年は東京大学や京都大学等の難関国立大学でも導入されるなど広がりを見せています。
学校推薦型選抜への出願を視野に入れているが、「推薦入試とは何が違うのか」「新しい入試に対する対策は何をすればいいのか」などの疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は2021年度から開始される学校推薦型選抜について、推薦入試と学校推薦型選抜の違い、学校推薦型選抜の概要、試験内容や対策、学校推薦型選抜対策ができる塾についてお話しします。
推薦入試と学校推薦型選抜の違い
2021年度入試、つまり2020年4月に高校3年生になった学年から、現行の推薦入試が学校校推薦型選抜に変わります。
この変更は高大接続改革の一環として行われているものです。
従来の推薦入試から学校推薦型選抜への変更にあたり、変わることは大きく分けて3つあります。
「推薦入試」から「学校推薦型選抜」に名称が変更となります。
「入試」から「選抜」という言葉に変更された理由は、これまでの「入試」は狭い意味の学力(知識や技能)のみを試すものとなっていたからです。
知識だけでなく、主体的に考えて行動できる幅広い意味での学力を持った人材を選抜していくという意図があり、「選抜」という言葉が採用されました。
調査書の内容
調査書は、受験者の学業成績や学習態度などを教員が記述する文書のことで、内申書とも呼ばれます。
大学側は、入学後の学びを積極的に行う意欲と能力のある学生を求めています。
それを見分けるための資料として調査書が使われているのです。
今までも提出は義務付けられていましたが、内容が見直され、これまでのような評定平均値だけではなく、特長や特技、部活動やボランティア活動、留学経験、取得資格や検定、表彰記録など勉学以外の様々な取り組みを詳細に記入することになりました。
高校生活において、勉学以外のことに積極的に取り組んだ生徒をより評価しやすくするという狙いがあります。
また、学業成績についても評定値だけでなく、志望学部の基礎科目の履修有無、成績の推移など、履修状況や成績の推移まで選抜基準に取り入れる大学が増える見込みです。
多面的評価の実施と大学入学共通テストの活用
大学によって「多面的評価」か「大学入学共通テスト」の、いずれか一方が必須と指定されます。
「多面的評価」は、小論文やプレゼンテーション、実技、学力テスト、資格・検定試験の成績など様々な方法で多面的に生徒を評価することを目的としています。
現行の推薦入試でもセンター試験の成績を選考に利用している大学があります。
2021年度入試からも基礎学力を確認する目的で、大学入学共通テストが活用される見込みです。
✔幅広い分野で「選抜」していく試験へ
✔調査書の実績や経験などの欄がより詳細に
✔「多面的評価」か「大学入学共通テスト」
学校推薦型選抜とは
そもそも、学校推薦型選抜とはどのような入試制度なのでしょうか。
学校推薦型選抜の出願条件・評価基準、種類についてまとめていきます。
出願条件・評価基準
学校推薦型選抜の一般選抜と比べて最も異なる点は、出身高校長の推薦を受けなければ出願ができないという点です。
出願にあたっては、学習成績の評定平均値の基準や「○浪」といった出願条件が設定されている場合もあるため、誰もが出願できる入試ではありません。
また、学校推薦型選抜は公募制推薦で一部例外はありますが、「出願者は合格した場合必ず入学する者に限る」という専願が基本となっています。
種類
学校推薦型選抜は様々なタイプの選抜があり、大きく分けると「公募制」と「指定校制」、そして「国公立型」と「私立型」の四種類に分けられます。
公募制
「公募制」は、大学の出願条件をクリアし、出身高校長の推薦があれば受験可能です。
全国の高校から広く出願することができ、既卒生の出願を可としている大学もあります。
公募制の中にも種類があります。
成績基準が設けられることが多く、募集定員が比較的多い「公募制一般入試」、スポーツや文化活動、委員会やボランティアなど課外活動での取り組んだことをアピールできる「公募制特別推薦選抜」です。
課外活動で実績のある人は公募制特別推薦選抜に挑戦するのもよいでしょう。
指定校制
「指定校制」は大学が指定した高校の生徒を対象とする選抜です。
私立大学が中心であり、国公立大学ではほとんど行われていません。
大学が指定した高校の生徒にのみ出願資格が与えられるため、現役生に限られます。
推薦枠は少人数なので、希望者が多い場合は校内で選考が実施され、成績、課外活動実績、生活態度などを基準に評価されます。
狭き門ですが、推薦枠を獲得さえすれば合格率は高いです。
また、一般選抜と大きく違う点として専願制の入試となっています(近年、他大学との併願が可能な併願制も増加傾向ではあります)。
指定校制は原則第1志望校に限った入試だということを理解しておきましょう。
国公立大学の学校推薦型選抜
国公立大学の学校推薦型選抜は、私立大学に比べて募集人員が少ないです。
さらに出願条件には「学習成績の評定平均値4.0以上」など成績基準が厳しい大学があります。
1高校からの推薦人数が制限されていることもあるので、出願前に学内で選抜が行われるケースも少なくありません。
選抜の際には共通テストの受験を課す大学と課さない大学の2タイプに大別され、その入試日程も大きく異なります。
私立大学の学校推薦型選抜
私立大学の学校推薦型選抜は、入学者比率が40%以上を占め、私立大学入学の大きな入り口となっています。
私立大学の出願要件は国公立大学ほど厳しくない場合が多く、成績基準を設定していない大学もあります。
選抜方法は、大学が小論文や適性検査、面接、基礎学力試験、調査書等の書類審査をさまざまに組み合わせて定めます。
近年は学力を測る試験を行っている大学も出てきています。
一般選抜と同様に特色のある多様な選抜方式が実施されています。
例えば、「スポーツ推薦」「有資格者推薦」「課外活動推薦」などがあります。
「スポーツ推薦」は、スポーツで実績を出した人を獲得することが目的で、出願基準は高校時代の競技成績です。
「有資格者推薦」は、実用英語技能検定(英検Ⓡ)やケンブリッジ英語検定といった英語資格や日商簿記などの技能をもつ受験生が優遇される選抜です。
「課外活動推薦」は、生徒会活動や部活動、ボランティア活動などで活躍した人を対象にした選抜となっており、コンクールや大会等での成績を基準とする大学も少なくありません。
✔基本的に専願のみ
✔指定校推薦はほとんど私立大学のみ
✔私立大学の学校推薦型選抜は多様な選抜方式
学校推薦型選抜の試験内容とは
試験内容は大学によって大きく異なります。
大学ごとに異なる試験内容に合わせて対策をしなければいけないのですが、今回は試験内容に含まれていることが多い試験とその対策をご紹介します。
試験内容
2021年度入試からは、学力の3要素である1. 知識・技能、2. 思考力・判断力・表現力、3. 主体性・多様性・協働性を問うことを意識した試験内容になります。
小論文など、受験者自らの考えに基づき、論理的に記述させる評価方法のほか、表現力を問うプレゼンテーション、口頭試問、技能を問う実技、知識を問う教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績、学力を確認する共通テストなどが実施されます。
すでに面接や小論文では学科に関連した専門的知識が問われることも珍しくありません。
学校型推薦入試の対策方法
学校型推薦入試は問われる内容が多いので、早めの対策が必要になります。
それでは、どのような対策をすればよいか4つのポイントにわけて解説します。
推薦書
推薦書は、高校3年時の担任が受験者の幅広い学力(思考力や表現力を生かし主体的に協働して学ぶ)を評価して書くものです。
生徒自身が書く資料(書類)とは別のものです。
「授業、宿題以外に自分でテーマを見つけて調査、研究してまとめた経験があるか」というような質問にも答えられるように、なるべく高校2年生までに成果を残しておくことが必要です。
事前に参考資料の提出を求められることも多くなると思われます。
調査書
学校推薦型選抜では、評定平均値が出願条件になります(例えば、3.5以上など)。
大学側はまず指導上参考になる事項を確認していきます。
新入試と同時に調査書が新しくなり、細かい記入欄が新設されました。
各教科・科目の時間の学習における特徴、行動の特徴・特技、課外活動経験、取得資格・検定等、表彰・顕彰の記録などです。
なるべくすべて埋まるようにしましょう。
資料(書類)
資料(書類)は、先生ではなく受験する生徒が書きます。
内容は大学が定めますが、志望理由や活動報告書、学修計画書(大学進学後どのような学びを得たいか)などの内容が予想されます。
あらかじめ志望大学でどのような内容が求められているか調べて早めに準備しておきましょう。
学力検査
文部科学省は学力検査の例として、共通テスト、小論文、プレゼンテーション、教科テスト、資格・検定などを挙げています。
特に小論文、教科テスト、口頭試問は採用されることが多いと予想されます。
小論文やプレゼンテーションはフィードバックを受けることが大切なので、高校や塾の先生など相談できる環境を作りましょう。
✔試験内容は大学によって異なる
✔経験や実績が問われることがある
✔相談できる環境が必要
学校推薦型選抜の対策ができる塾
学校推薦型選抜の対策には、ただ勉強を教えるのではなく一人一人の志望大学、そして適性や長所を理解してくれる塾を選択することが重要です。
ですので、今回は学校推薦型選抜に必要な一人一人にカリキュラムを作ってくれる学習塾を紹介します。
個別教室のトライ

| 個別教室のトライの基本情報 | |
|---|---|
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 授業形式 | 1対1の個別指導 |
| 校舎 | 全国607教室 |
| 特徴 | 厳選されたプロ講師陣による全国No.1の個別指導塾 |
個別教室のトライの特徴
個別教室のトライは個別指導の塾で、直営教室数は全国でNO.1です。
個別教室のトライの講師は完全マンツーマンで専任制なので、同じ講師が継続して指導を行います。
生徒一人に先生一人なので、生徒の弱点を的確に把握し、効率的に成績を伸ばすための指導が受けられます。
指導実績は120万人で、「大学受験のための受験勉強がしたい」「苦手な科目を克服したい」「不登校の悩みを解決したい」などのどのような目標・目的に対してもプランを作成するメソッドがあります。
「学校推薦型選抜を受けたいので定期テストの点数をとにかく上げたい」という場合でも対応が可能です。
評定を上げるために定期テストの点を上げるには、生徒の通っている高校のテストに対して対策をしなければいけません。
集団指導の塾だと一人一人の通っている学校に特化した指導は難しいですが、個別指導の塾なら柔軟にカリキュラムを構成して指導してくれます。
翔励学院
ここでは、翔励学院の特徴と基本情報について見ていきましょう。
| 翔励学院の基本情報 | |
|---|---|
| 対象学年 | 中学生~社会人 |
| 授業形態 | マンツーマン個別指導 |
| 対応している入試形態 | 小論文 |
| 校舎 | 渋谷教室 |
小論文を徹底的に対策できる
翔励学院は小論文を徹底的に対策できる学習塾として知られており、大学入試を中心としてさまざまな生徒が活用しています。
特に大学推薦入試では小論文が課せられていることは多く、しっかりと対策しておかないと小論文が原因で落ちてしまったということになりかねません。
また、難易度の高い大学になればなるほど小論文のテーマも難しくなっていくため、しっかりとした指導が必要になってきます。
翔励学院はマンツーマン指導にて生徒の志望校に合わせた小論文対策が行えるため、気になる方はチェックしてみてください。
面接対策や進路指導も受けられる
翔励学院は小論文の対策はもちろん、面接対策や志望理由書の書き方なども指導しています。
小論文などと合わせて課せられることが多い面接も対策することができるのは大きな強みといえます。
また推薦入試は志望理由書などから戦いが始まっているといっても過言ではなく、それら提出書類のサポートもしてくれます。
そのため、小論文をはじめ推薦入試にて大学受験を考えているなら、まずは利用を検討したい学習塾といえるでしょう。
Loohcs志塾
| 対象学年 | 高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 集団指導 |
| 対応している入試形態 | 総合選抜型・AO推薦入試・一般入試 |
| 校舎 | 渋谷本校・新宿代々木校・三田校・池袋校・町田校・吉祥寺校・下北沢校・ 目黒校・自由が丘校・上野校・御茶ノ水・秋葉原校・新小岩校・柏校(千葉)・ 横浜校(神奈川)・青葉台校(神奈川)・藤沢校・仙台校(宮城)・大阪中津校(大阪)・京都四条校(京都)・西宮北口校(兵庫)・姫路校(兵庫)・名古屋校(愛知)・ 福岡天神校(福岡)・沖縄校・オンライン校 |
どんな推薦でもLoohcs志塾がおすすめ
Loohcs志塾は、さまざまな推薦入試の対策に特化した大学入試のための塾です。
そのため、学校推薦型選抜の対策もばっちり行えます。
学校推薦型選抜の場合、試験科目は大学によって異なるため、志望大学に合わせて入試対策をしなければなりません。
Loohcs志塾では、大学別に対策を行うだけでなく、各科目に関しても入試対策を行えるため、入試対策でやるべきことが明確になり、学習を進めやすくなります。
ワンランク上の小論文対策講座
高校の授業では、基本的に小論文の授業はありません。
せいぜい、現代国語の時間に作文を書く程度です。
そのため、学校推薦型選抜の試験科目のひとつとして、小論文のテストを受けなければならなくなった際、塾などで勉強していなければ入試に合格するのは難しくなります。
ですが、Loohcs志塾であれば、プロが対策を行った小論文対策講座で小論文について勉強ができます。
小論文には、作文とは異なったルールがいくつもあり、書くためにはテクニックが必要です。
Loohcs志塾の講師は、お子様に合わせて指導を行っています。
また、小論文がきちんと書けなかったときには、書けなかった理由やどう書くべきだったかについて講師と一緒に考える指導も行っているため、次のテストに活かせる実力がつきます。
まとめ
学校推薦型選抜は現行の推薦入試より幅広い学力が問われる内容に変わりました。
調査書や資料(書類)に記入する内容が充実したので、経験や実績があれば有利になるでしょう。
学力だけでなく、高1から高3にかけての人間的成長や自分から動いた経験などが評価されるようになるので、早い時期からの対策が必要になってきます。
他者とコミュニケーションをとって何かを成し遂げる協働性や、自分で考え、判断して動くことができる主体性を活かして挑戦した記録や実績が評価されます。
早めに方針ややるべきことをアドバイスしてくれる学習塾などを見つけて、相談できる環境を作っておくと良いでしょう。
学校推薦型選抜について
この記事の内容が一目でわかります。
学校推薦型選抜ってなに?
学校推薦型選抜とは公募制と指定校制に分かれた入試制度です。
詳しくは記事内のまとめてあります。
学校推薦型選抜の試験内容は?
学校推薦型選抜の試験内容は資料や調査書・学力試験が課せられます。
記事内で詳しくまとめているので参考にしてください。
学校推薦型選抜の対策が可能な塾は?
学校推薦型選抜の対策が可能な塾は総合型選抜専用塾AOIです。
StudySearchでは、塾・予備校・家庭教師探しをテーマに塾の探し方や勉強方法について情報発信をしています。
StudySearch編集部が企画・執筆した他の記事はこちら→
受験・資格に関する新着コラム
-
 italkiとは?料金形態や口コミ、選ばれる理由を徹底解...
italkiとは?料金形態や口コミ、選ばれる理由を徹底解...本記事では、italkiに関する料金形態や口コミ・評判、選ばれる理由や特徴を徹底解説しています。オンラインで英語学習を行いたい方などに最適な英語学習プラットフォ...
-
 多様なニーズに対応した学習塾Enducateの費用や口コ...
多様なニーズに対応した学習塾Enducateの費用や口コ...個別指導の新しい形とは?プロ講師のみの質の高い授業が受けられる、ニーズに合わせた新しい形の学習塾 Enducateの特徴や実績・気になる費用もご紹介!
-
 春期講習を無料で受けられる塾12選!費用の抑え方や料金相...
春期講習を無料で受けられる塾12選!費用の抑え方や料金相...春期講習が無料で受けられる塾を紹介しています。 春季講習の料金相場や費用の抑え方tについても解説しています。
-
 春期講習で家庭教師を選ぶメリットとは?おすすめの家庭教師...
春期講習で家庭教師を選ぶメリットとは?おすすめの家庭教師...本記事では、春期講習で家庭教師を選ぶメリットや家庭教師の選び方、おすすめの家庭教師まで徹底的に解説しています。家庭教師の選び方がわからない方や人気の高いおすすめ...
受験・資格に関する人気のコラム
-
 大学無償化とは?条件や支援内容・手続き方法・メリット・注...
大学無償化とは?条件や支援内容・手続き方法・メリット・注...令和2年4月1日から実施の大学無償化についてご存知でしょうか。本記事では家庭での資産/年収での要件や手続き方法・支援によるメリット等を解説します。詳しい内容につ...
-
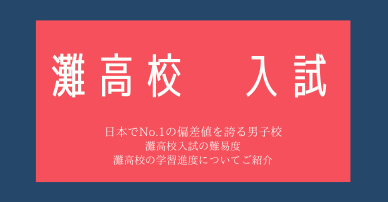 偏差値79|灘中学校・高等学校を解説!偏差値・難易度・入...
偏差値79|灘中学校・高等学校を解説!偏差値・難易度・入...今回の記事は7割が東大入学実績を誇る灘高校についてまとめました。男子校・中高一貫校である灘高校受験の難易度や高校の学習進度について徹底解説いたいします。
-
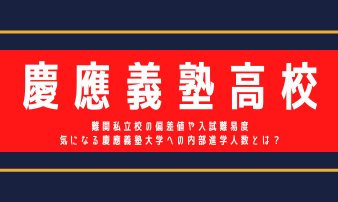 【2026年度】慶應義塾高校を徹底解説!偏差値や入試の難...
【2026年度】慶應義塾高校を徹底解説!偏差値や入試の難...今回の記事は、慶應義塾が経営・運営する中高一貫の男子校である慶應義塾高校の偏差値や入試の難易度についてご紹介します。高校から慶應義塾大学に内部進学する人数や授業...
-
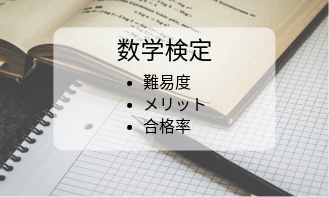 数学検定の難易度や勉強法、メリットとは、合格率や各級のレ...
数学検定の難易度や勉強法、メリットとは、合格率や各級のレ...数学検定の難易度や合格率とは?受けても意味がない?受けることで得られるメリットとは?今回は、そんな印象を持たれる数学検定について詳しく説明していきます。数学検定...